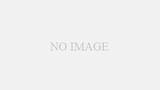日本の雇用統計
調査概要
労働力調査(基本集計)は、総務省統計局が毎月実施する基幹統計調査で、2025年5月の速報結果が公表されました。本調査は、15歳以上の全国の労働力人口を対象に、就業状況や失業状況を把握するものです。調査対象期間は2025年5月の最終1週間で、約4万世帯を対象に実施されました。以下は、2025年5月の主要な結果をまとめたものです。
主要指標
2025年5月の労働力調査(季節調整値)に基づく主要な指標は以下の通りです
- 就業者数:6,742万人(前年同月比+33万人)。就業者数は増加傾向が続き、過去最高水準を維持しています。特に、サービス業や製造業での雇用増加が顕著です。
- 完全失業者数:171万人(前年同月比-7万人)。完全失業率は2.5%で、前月に比べ横ばいながら、安定した低水準を維持しています。
- 労働力人口:6,913万人。労働力人口は微増傾向にあり、女性や高齢者の労働参加が進んでいます。
- 非労働力人口:4,108万人。非労働力人口は減少傾向にあり、労働市場への参加が進んでいることを示唆しています。
雇用形態別の動向
雇用形態別の動向は以下の通りです
- 正規雇用:3,572万人で、前年同月比+25万人。安定した雇用環境が続き、正規雇用の増加が顕著です。
- 非正規雇用:2,089万人で、前年同月比+8万人。パート・アルバイトや派遣労働者の増加が見られ、特に女性の非正規雇用が増加傾向にあります。
- 自営業者等:943万人で、前年同月比ほぼ横ばい。個人事業主やフリーランスの数は安定しています。
産業別の就業状況
産業別の就業者数の動向は以下の通りです:
- サービス業:宿泊業・飲食サービス業で就業者数が回復傾向にありますが、依然としてコロナ前の水準には届いていません。
- 製造業:製造業は堅調な雇用増加を示し、輸出関連産業での求人需要が拡大しています。
- 建設業:建設業は人手不足感が強く、就業者数の増加が続いています。
性別・年齢別の労働参加
性別および年齢別の特徴は以下の通りです:
- 女性の労働参加:女性の就業者数は2,989万人で、前年同月比+20万人。女性の労働力参加率は53.2%で、過去最高を更新しました。特に、25~34歳の女性の労働参加が顕著です。
- 高齢者の労働参加:65歳以上の就業者数は912万人で、前年同月比+10万人。高齢者の労働参加が進む一方で、健康や働き方の柔軟性が課題となっています。
地域別の雇用動向
地域別の雇用状況は、都市部と地方部で若干の差が見られます。都市部(特に首都圏)ではサービス業や情報通信業の求人が堅調で、完全失業率は2.3%と低水準です。一方、地方部では農業や観光関連産業の回復が遅れており、完全失業率は2.7%とやや高めです。
労働市場の課題と展望
2025年5月の雇用統計からは、労働市場の回復が継続しているものの、以下のような課題が浮き彫りになっています:
- 人手不足:建設業や医療・福祉分野での人手不足が深刻化しており、労働力の確保が課題です。
- 賃金上昇の遅れ:雇用回復にもかかわらず、賃金上昇は緩やかで、実質賃金の低下が懸念されます。
- 働き方の多様化:テレワークや副業の普及が進む中、柔軟な労働環境の整備が求められています。
今後、外国人労働者の受け入れ拡大やデジタル技術を活用した労働生産性の向上が、持続可能な労働市場の構築に寄与すると期待されます。
20年前(2005年)との比較
調査概要
日本の雇用統計は、総務省統計局による「労働力調査」を基に作成され、労働市場の動向を把握するための重要な指標です。2025年5月の最新データ(季節調整値)と、20年前の2005年5月のデータを比較することで、労働市場の長期的な変化を分析します。以下では、就業者数、失業率、雇用形態、産業構造、労働参加率などの観点から比較を行います。
就業者数と労働力人口
2025年5月:就業者数は6,742万人、労働力人口は6,913万人。女性や高齢者の労働参加が進み、就業者数は過去最高水準を維持しています。
2005年5月:就業者数は6,360万人、労働力人口は6,650万人。20年間で就業者数は約382万人増加し、労働力人口も約263万人増加しました。これは、少子高齢化にもかかわらず、女性や高齢者の労働市場への参加が進んだ結果です。特に、2025年には65歳以上の就業者数が912万人に達し、2005年の約500万人から大幅に増加しています。
完全失業率
2025年5月:完全失業率は2.5%で、安定した低水準を維持しています。完全失業者数は171万人で、前年比7万人減。
2005年5月:完全失業率は4.4%、完全失業者数は約300万人。20年前と比較すると、失業率は1.9ポイント低下し、失業者数は約129万人減少しました。これは、景気回復や労働市場の構造変化、企業の雇用維持策の進展によるものです。ただし、2025年の低失業率は人手不足による求人需要の増加も反映しています。
雇用形態の変化
2025年5月:正規雇用が3,572万人、非正規雇用が2,089万人。正規雇用は前年比25万人増、非正規雇用は8万人増。非正規雇用の割合は約31%で、女性や高齢者の非正規雇用が増加。
2005年5月:正規雇用が約3,500万人、非正規雇用が約1,700万人。非正規雇用の割合は約27%でした。20年間で非正規雇用の割合が4ポイント上昇し、非正規雇用者数は約389万人増加しました。これは、労働市場の柔軟化やサービス業の拡大、女性の労働参加増加による影響が大きいです。
産業構造の変化
2025年5月:サービス業(特に医療・福祉や情報通信業)が就業者数の多くを占め、製造業も輸出関連で堅調。建設業は人手不足が顕著です。
2005年5月:製造業が就業者数の大きな割合を占め、サービス業は現在ほど多様化していませんでした。20年間で、製造業の就業者数は約1,200万人から約1,000万人に減少し、サービス業(特に医療・福祉)が約1,200万人から約1,800万人に増加しました。デジタル化や高齢化に伴う需要変化が、産業構造の転換を促しています。
性別・年齢別の労働参加
2025年5月:女性の就業者数は2,989万人(労働力参加率53.2%)、65歳以上の就業者数は912万人。女性や高齢者の労働参加が顕著に進展。
2005年5月:女性の就業者数は約2,600万人(労働力参加率約48%)、65歳以上の就業者数は約500万人。女性の労働力参加率は5.2ポイント上昇し、就業者数は約389万人増加。高齢者の労働参加も大幅に増加し、年金制度改革や健康寿命の延伸が背景にあります。
地域別の動向
2025年5月:都市部(特に首都圏)の完全失業率は2.3%、地方部は2.7%。都市部ではサービス業や情報通信業が牽引し、地方部では観光や農業の回復が課題。
2005年5月:都市部と地方部の失業率格差は現在ほど顕著ではなく、全国平均で4.4%。都市部の雇用回復が先行し、地方部の雇用環境は相対的に停滞していました。20年間で、都市部の労働市場はより多様化し、地方部では人手不足が課題となっています。
労働市場の課題と展望
2025年の雇用統計は、2005年と比較して以下のような特徴が明らかです
- 労働参加の拡大:女性や高齢者の労働参加が進み、労働力人口が増加。ただし、少子高齢化による労働供給の制約は今後も課題。
- 非正規雇用の増加:柔軟な働き方が広がった一方で、賃金格差や雇用の安定性が問題に。
- 産業構造の転換:サービス業へのシフトが進む中、デジタルスキルや高齢者向けサービスの需要が増加。
- 人手不足:2025年は建設業や医療・福祉分野での人手不足が顕著で、2005年よりも労働市場の逼迫感が強い。
今後、外国人労働者の受け入れ拡大、テレワークや副業の普及、AI・自動化技術の導入が労働市場にさらなる変化をもたらすと予想されます。2005年から2025年にかけての労働市場の進化は、経済構造の変化と働き方改革の成果を反映していますが、持続可能な雇用環境の構築には、賃金上昇やスキル向上支援が不可欠です。
30年前(1995年・就職氷河期)との比較
調査概要
日本の雇用統計は、総務省統計局の「労働力調査」を基に作成され、労働市場の動向を把握する重要な指標です。2025年5月の最新データ(季節調整値)と、30年前の1995年5月(バブル崩壊後の就職氷河期の始まり)のデータを比較することで、労働市場の長期的な変化を分析します。就職氷河期(1993~2004年頃)は、企業が新卒採用を大幅に抑制し、若年層の就職難が深刻化した時期です。以下では、就業者数、失業率、雇用形態、産業構造、労働参加率、氷河期世代の影響を比較します。
就業者数と労働力人口
2025年5月:就業者数は6,742万人、労働力人口は6,913万人。女性や高齢者の労働参加が進み、就業者数は過去最高水準を維持しています。労働力人口は少子高齢化による縮小圧力を、女性や高齢者の参加で補っています。
1995年5月:就業者数は約6,500万人、労働力人口は約6,800万人。30年間で就業者数は約242万人増加、労働力人口は約113万人増加しました。1995年はバブル崩壊後の不況で雇用が停滞し、新卒採用が大幅に縮小された時期でした。2025年の労働力人口の増加は、女性(特に25~34歳)や高齢者(65歳以上)の労働参加の拡大によるものです。
完全失業率
2025年5月:完全失業率は2.5%、完全失業者数は171万人。失業率は低水準で安定し、人手不足による求人需要が背景にあります。
1995年5月:完全失業率は約3.2%、完全失業者数は約210万人。30年前と比べ、失業率は0.7ポイント低下、失業者数は約39万人減少しました。1995年はバブル崩壊後の景気低迷で、特に新卒や若年層の失業が深刻化し、就職氷河期の初期として知られています。2025年の低失業率は、労働市場の逼迫と高齢者雇用の増加を反映しています。
雇用形態の変化
2025年5月:正規雇用が3,572万人、非正規雇用が2,089万人(非正規割合約31%)。非正規雇用は女性や高齢者の増加により拡大し、正規雇用も堅調に推移。
1995年5月:正規雇用が約4,000万人、非正規雇用が約1,200万人(非正規割合約18%)。30年間で非正規雇用者の割合が13ポイント上昇、約889万人増加しました。1995年は正規雇用中心の労働市場でしたが、氷河期の影響で非正規雇用が増加し始めました。この時期、新卒が正規雇用の機会を失い、派遣や契約社員として働くケースが増加し、後の「氷河期世代」の不安定な就労環境の要因となりました。
産業構造の変化
2025年5月:サービス業(特に医療・福祉、情報通信業)が就業者数の中心で、約1,800万人。製造業は約1,000万人で、輸出関連の回復が寄与。建設業は人手不足が顕著です。
1995年5月:製造業が約1,500万人と主要な雇用分野で、サービス業は約1,000万人。30年間で製造業の就業者数が約500万人減少し、サービス業が約800万人増加しました。1995年は製造業の雇用がまだ強く、グローバル化やIT革新による分業化が始まる前でした。2025年は高齢化に伴う医療・福祉需要やデジタル化の進展が、産業構造の転換を加速させています。
性別・年齢別の労働参加
2025年5月:女性の就業者数は2,989万人(労働力参加率53.2%)、65歳以上の就業者数は912万人。女性や高齢者の労働参加が大きく進展しました。
1995年5月:女性の就業者数は約2,500万人(労働力参加率約46%)、65歳以上の就業者数は約400万人。女性の労働力参加率は7.2ポイント上昇、就業者数は約489万人増加。高齢者の就業者数は約512万人増加しました。1995年は女性の社会進出が限定的で、高齢者雇用も現在ほど進んでいませんでした。氷河期世代(1970~1982年生まれ)は、2025年時点で43~55歳となり、依然として非正規雇用や不安定な就労環境に直面する人が多いです。
就職氷河期世代の影響
2025年5月:氷河期世代(現在43~55歳)は、正規雇用の機会を逃した影響で、非正規雇用や低賃金の職に就く割合が高いです。2018年の労働力調査では、35~44歳の非就業者(就労せず、家事・通学もしていない)が約40万人(人口の2.4%)に上ると推計されており、引きこもりや不安定雇用の問題が続いています。政府は2020年から「就職氷河期世代支援プログラム」を実施し、正規雇用者30万人増を目指しましたが、成果は限定的です。
1995年5月:氷河期世代(当時13~25歳)は新卒採用の縮小に直面し、就職内定率が低下。特に大学卒業者(1970~1982年生まれ)は、正規雇用を得られず、派遣やアルバイトに頼るケースが急増しました。この時期の有効求人倍率は約0.6倍と低く、企業が新卒採用を大幅に抑制したため、「ロストジェネレーション」とも呼ばれる世代が生まれました。2025年時点で、この世代の経済的・社会的影響(未婚化、晩婚化、低賃金など)が続いています。
労働市場の課題と展望
2025年5月と1995年5月の比較から、以下の特徴が明らかです:
- 労働市場の逼迫:1995年の高い失業率(3.2%)に対し、2025年は2.5%と低く、人手不足が顕著。特に建設業や医療・福祉での労働力不足が課題。
- 非正規雇用の拡大:1995年の18%から2025年は31%に上昇。氷河期世代の非正規雇用の増加が、賃金格差や生活不安定化の要因に。
- 女性・高齢者の労働参加:2025年は女性と高齢者の労働参加が大きく進展。1995年は女性の社会進出が限定的で、高齢者雇用も少なかった。
- 氷河期世代の課題:1995年に新卒だった氷河期世代は、2025年時点で中高年層として低賃金や非正規雇用の問題に直面。政府の支援策は進むが、抜本的な解決には至っていません。
- 賃金と物価:1995年から2025年まで、平均年収は約440~460万円でほぼ横ばい。社会保険料負担は1995年の約11.5%から2023年で18.7%に上昇し、実質手取り収入は減少傾向。
2025年の労働市場は、1995年の氷河期と比べ雇用環境が改善しているものの、氷河期世代の課題(非正規雇用の多さ、賃金停滞、晩婚化など)が長期的な影響を及ぼしています。今後、外国人労働者の受け入れ、デジタルスキル教育、柔軟な働き方の推進が、労働市場の持続可能性を高める鍵となります。氷河期世代への支援強化も、経済的格差の是正に不可欠です。